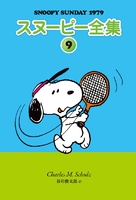スヌーピーとチャーリー・ブラウン。日本中誰もが知っている親しみ深い顔ぶれですよね。40年前にはじめて日本で紹介されてから、キャラクターの愛くるしさで今もなお大人気のスヌーピーですが、彼らがアメリカの新聞掲載マンガから生まれたキャラクターだということ、皆さんはご存じでしたか?
コミック『PEANUTS(ピーナッツ)』は、1950年から新聞7紙のデイリー版とサンデー版に掲載され、作者チャールズ・M・シュルツさんが1999年に引退されるまで、長期に渡り連載されました。
世代を超えて愛されるキャラクターたちの日常を描いた『PEANUTS』。とっても味わい深い作品なんです。
スヌーピーは知っているけど原作は読んだことがないというかたがいたらもったいない!
この度、1971年から1980年までに新聞のサンデー版に掲載されたコミックを全て読める唯一の本、『スヌーピー全集』が、ついに復刻販売されました。日本語訳は、出版当初から翻訳を手がけられている詩人・谷川俊太郎さん。谷川さんの訳とともに、『PEANUTS』の世界をこころゆくまで楽しめる全集です。
発売を記念して、谷川俊太郎さんにお話を伺いました!
かわいくてちょっとなつかしい ≪70年代サンデー版コミックス≫のスヌーピーたちに、また会える! スヌーピーやウッドストック、チャーリー・ブラウンなど、世代を超えて愛されるキャラクターたちがおりなす大人気コミック『PEANUTS』。1971年から1980年まで、新聞の≪サンデー版≫に掲載されたコミックをすべて読める唯一の本、『スヌーピー全集』がついに復刻! 谷川俊太郎先生の味わいある日本語訳とともに、永遠のスタンダード『PEANUTS』の世界をこころゆくまで楽しめる全集です。
●スヌーピーとその仲間たち


●復刻版「スヌーピー全集」
───今回の復刻発売は、復刊を望む多くの声に後押しされて、という形だと伺いました。谷川さんの今のお気持ちをお聞かせいただけますか?
谷川:デイリー版がショートショートだとすると、サンデー版はミニサイズの一幕ものとも言えそうです。新聞連載の日々の流れの中で読むのとはまた違った形で、独立して読んでもらえるのを嬉しく思います。
●「ピーナッツ」との出会い
───谷川さんが初めて「ピーナッツ」に出会ったのはいつ頃、どんな形でだったのでしょうか。
谷川:1960年代、日本で英字紙に載っているのをちらちら見ていました。1966年から67年にかけて、しばらく合衆国で暮らしたことがあり、その頃から新聞を買うとまずマンガ欄を見るようになって、「ピーナッツ」の面白さに目覚め始めました。
───英語で読まれた初めての「ピーナッツ」の印象を教えてください。
谷川:登場人物たちのポーカーフェースっぽい表情と、まったく子どもを意識していないウイッティな台詞の魅力。
───今では誰もが知っているキャラクター「スヌーピー」ですが、初めてその世界を日本の読者に引き合わせたのは、谷川さんだと伺っています。翻訳を手がけられるまでの経緯を教えていただけますか?
谷川:日本へ戻ってしばらくして、知り合いの出版社の社長さんが、「ピーナッツ」を翻訳しないかと言ってきました。英語は高卒程度の能力しかないし、私はアメリカ風俗にも詳しくないので二の足を踏みましたが、スヌーピーという変な犬が気に入っていたので、英語を母語とする日系二世の女性に下訳と監修をお願いして、翻訳を始めました。
───そのあと、長年にわたり翻訳を担当されることとなった「ピーナッツ」とは、やはり“ご縁”があるのでしょうか。
谷川:出版社が次々「ピーナッツ」から撤退した時代もありましたし、新しい翻訳者で出た本もありましたし、他の仕事に忙しくなって、私が翻訳者を辞退したいと言い出したこともありましたが、「ピーナッツ」とのご縁は切れませんでした。


第1巻には、1971年に執筆されたコミックを収録。めずらしい「日本語ふきだし(+英語原文)」で、谷川俊太郎さんの名訳を、ビジュアルでもより楽しめます。巻頭には豪華カラー版のコミックが収録。
© 2013 Peanuts Worldwide LLC













 【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪
【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪